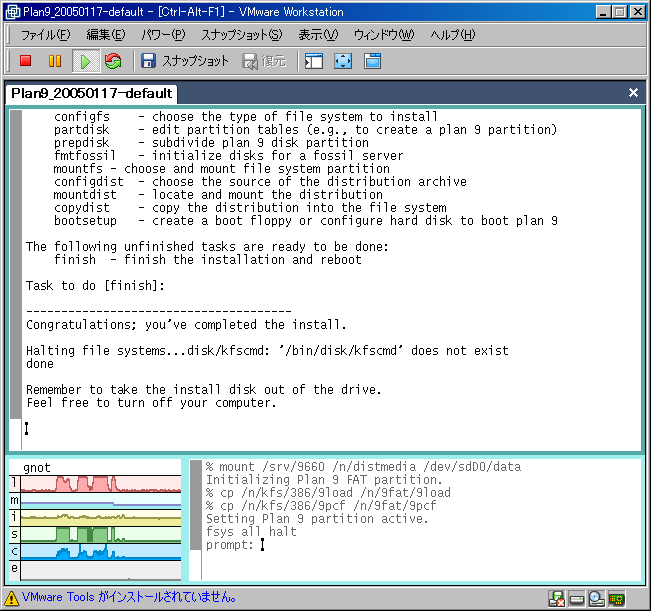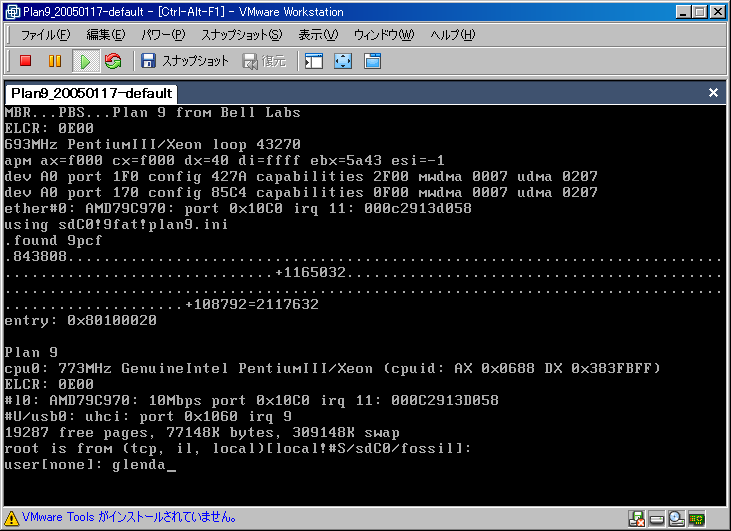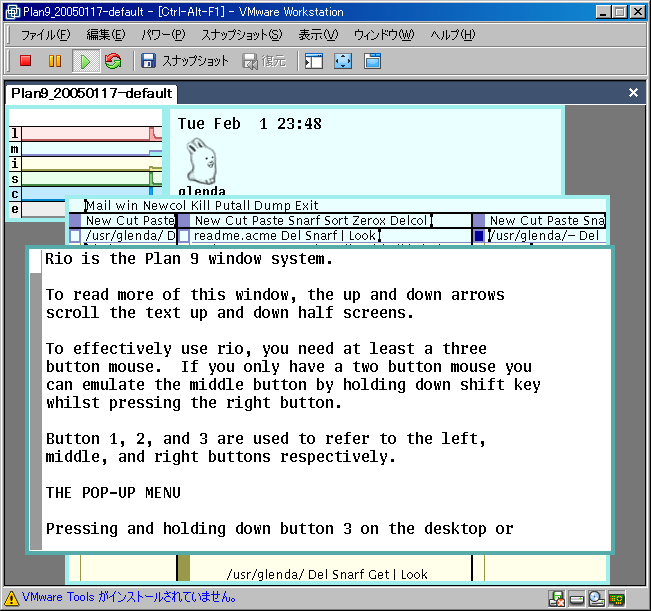@ITにて、仮想マシンの記事が、掲載されていたので反応してみます。
まずは、これ。
http://www.atmarkit.co.jp/fsys/kaisetsu/053virtual_machine/virtual_machine.html
う〜ん、ごくごく普通の仮想マシンの使い方ですね。
これといって、特筆するようなものはなし。
ただ、
シナリオ3:OSイメージのバックアップをとる
は、結構便利かもと思いました。
サーバのディスクイメージってとるの大変ですから、こんな感じで
さくっとイメージとれるのはすばらしいことだと思います。
ほんとに、これだけでも使う価値ありですね。
そして、最後に、書いてありました。
これです、これ。これが、仮想マシンの真髄です。
複数のサーバをまとめて、リソース・プールを作成し、そこから必要なリソースをアプリケーションが得るような仮想化技術が普及することになるだろう。
聞いたことあると思います、これと同じことを言っているシステムって。
そうです、「グリッド」です。
実は、この手の技術って、こういう使い方なんですよね。今の流れって。
私の求めているシステムは、これなんです。この辺の突っ込んだ話は
いずれまた。
続いて、こちら。
http://www.atmarkit.co.jp/flinux/special/vm/vm01.html
こちらは、もう少し、大きな概念の説明ですね。
非常にわかりやすく、よくまとまっています。
そして、どうやら目玉になっているようですが「仮想マシンモニタ Xen」。
これ、これがすごいんです。「専用モニタを用いる仮想マシン」の解説を
読んでみてください。
どうでしょ?これも、「グリッド」を彷彿とさせませんか?
これを踏まえて、こちら。
http://www.computerworld.com/hardwaretopics/hardware/server/story/0,10801,98814,00.html?source=NLT_LIN&nid=98814
Xenが、RedHatとSUSEに、載ってくるらしいのです。
もし、本当に載ってくるとすれば、これらのOSをインストールした時点で
グリッドのリソース候補マシンの完成です。
Xenに関しては、すでに動いているおもしろいネットワークもあるので、
そのへんを含めて、いずれ書こうかなと思います。
はっきり言って、この辺は、すごいです。
近いうちにXenの記事を出すそうなので、かなり、期待です。
おまけ
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0502/08/news023.html
Cellが、発表されてようです。
こちらは、言わずとしれたPS3&グリッドコンピューティング用のプロセッサです。
記事中央付近に、「仮想化技術」の文字が。。。
IntelでいうところのVanderpool Technologyがデフォルト装備されていると
みてよさそうです。
これからみるに、グリッドを実現するアーキテクチャ的には、上で解説している
ようなXenなどのアーキテクチャを元にやるようですね。
やはり、グリッドは、仮想化からってことですね。
しかし、スペック見るほど、化け物プロセッサですね、これ。
PPC完全互換と言うことは、某MacXが走る可能性が。これは、すごいかも。
もちろん、YellowDogLinuxなんかも動く可能性もあるわけで。
どこか、PC汎用パーツが使えるようなマザーボード出してくれないかしらん。